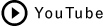馬渡島教会/MADARAJIMA

| お知らせ | |
|---|---|
| 教会名 | 馬渡島教会/MADARAJIMA |
| 教会堂名 | 聖ベルナルド |
| 住所 | 〒847ー0405 唐津市鎮西町馬渡島 1767-2 |
| TEL / FAX | 0955-82-9044/0955-82-3126 (呼子教会FAX) |
| ホームページ | 無 |
| facebookページ | 無 |
| 教会へのアクセス | 馬渡港 徒歩30分 |
| 担当司祭(主) | アルビン・ドゥゴシュ(ポーランドPRZEMYSL教区) |
| 担当司祭(協働/協力) | |
| ミサ時間(平日) |
水 18:30/木 6:00 |
| ミサ時間(主日) |
土曜日19:00 日曜日7:30 |
| ミサ時間(手話) | |
| ミサ時間(外国語) | |
| 障がい者施設 | |
| 講座・活動内容 | |
| 教会からのご案内 | |